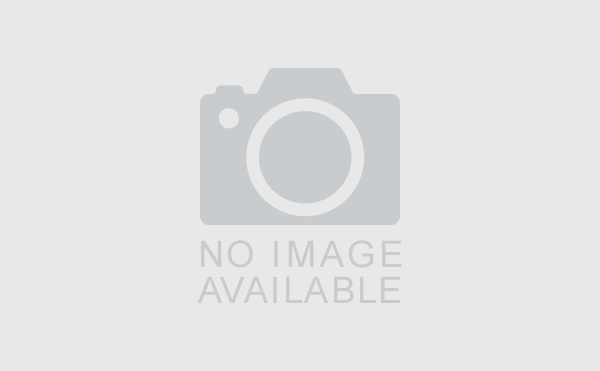杉本23)「第2回宝塚歌劇観劇の集い」に参加して・・・17号
「大坂慶應倶楽部主催〔第2回宝塚歌劇観劇の集い〕に参加して」
杉本 知瑛子(H.9、文・美 卒)
2015年10月31日(土)、大坂慶應倶楽部主催「第2回宝塚歌劇観劇の集い」に参加した。
今回は花組の公演で『新源氏物語』である。
歌劇は15時開演で18時30分より歌劇場内3階にある“エスプリホール”でのレセプションとなっている。
前回の歌劇は『ルパン3世』で、ルパン達現代人がフランス革命前の王朝にタイムスリップしての活躍となり、マリーアントワネットや宮廷貴族等の出演時間も長く“ベルばら”かと思えるような華やかな舞台構成であった。今回は日本の古典文学No.1と言える紫式部の超大作であり、絶世の美男子・光源氏に宝塚の男役トップスターが挑むのである。
これはもう期待しないほうが不思議である。
平安朝の宮廷や貴族の美しい衣装は宝塚らしい豪華絢爛な「絵巻物」となり、匂い立つような美しさの光源氏はロマンティックな愛と苦悩の姿を表現するのである。期待が膨らんでゆく。
本来『源氏物語』のテーマは壮大であるが、それゆえ今までの宝塚歌劇ではその一部分を『源氏物語』として取り扱い、数々の名作を誕生させてきた。
1)1919年:宝塚最初の源氏物語。『源氏物語 賢木の巻』:全編セリフ無し、歌のみの作品。
2)1952年:春日野八千代が気品高く光源氏を演じた『源氏物語』:話題となった作品である。
(白井鉄造 構成・演出:紫の上役は八千草薫)
3)1981年:『新源氏物語』月組初演:月組公演(柴田侑宏 脚本・演出)
4)1989年:『 同上 』月組再演:同上 ( 同上 )
5)2000年:人気漫画が原作『源氏物語 あさきゆめみし』
6)2008年:『夢の浮橋』(最終章の宇治十帖を題材にしたもの)
7)2015年:『新源氏物語』花組公演(柴田侑宏 脚本)
今回の『新源氏物語』はまさしく絵巻物そのもののようで、豪華絢爛な舞台であった。
桐壺帝の第二皇子として生まれた光源氏は、幼い頃に母と死別し亡き母と生き写しのような帝(実父)の妃である藤壺の女御に母の面影を追い求め慕うが、叶わぬ思いに苦しみながら華やかな 女性遍歴を重ねてゆく物語である。
帝も光源氏の幼少時は妃に「失礼だと思わずにいとおしみなさい。母子として似つかわしくなくはない」とお二人をこの上なくかわいがっておられたが、光源氏も元服後はもう御簾の内側には入れない。琴と笛の音に心を通わしあい、かすかに漏れてくる女御のお声を慰めとするのみであった。
しかし、ついに光源氏は藤壺への思いを抑えきれず、禁断の一夜を共にするのである。
「二人して罪に落ちましょう」恋の情熱と愛に生きる男の決意が、不義の子の懐妊となるのである。もう逢瀬は許されない。内に秘めた狂おしい恋心。むなしさを埋めようとして様々な女性と関係を持つ光源氏。しかし心は愛しい人の面影を追い求めている・・・と誰もに本心を疑われるのである。
プライドの高い正妻葵上、嫉妬と憎悪に狂う六条御息所、理想の女性としての純真な紫の上、等々複雑な人間模様がドラマティックに展開されていく。
時は過ぎ、政治の要職に就いた壮年の光源氏は女三の宮を正妻に迎える。
しかし、その若い新妻は他の男(頭の中将の長男・柏木:女三の宮の懐妊がきっかけで源氏に不義が知られ、苦悩のうちに若くしてこの世を去る)と密通して懐妊する。
まさに因果応報、桐壺帝が源氏と藤壺女御(後の中宮)の不義の子を帝の子(後の冷泉帝)と認めたように、光源氏も苦悩の末、柏木と女三の宮の不義の子を自分の実子(薫)として受け入れたのである。
歌劇の内容はここまでであった。
宝塚らしくテーマは男女の愛のみで、政治的な確執には全く触れていない。
そしてこの壮大な物語を約一時間四十分で完結させるため、ソロの歌は無し?セリフも少々・・・?
有名な場面はあれもこれも取り上げられているのだがその場面は数分で、はい!次の巻の場面へ!となる。
(多分「紅葉賀」の巻ではないかと思ったのだが)光源氏が宮廷舞楽の舞台に立っても十秒位で、舞も音楽(舞楽用の音楽)も無し。???で、衣装を見せるだけで、はい!お次の場面へ。あ~ぁ・・・
音楽は初めから終わりまで大音量のバンド演奏のみ。笙篳篥とまでは言わないがせめて、少しだけでも静かな日本の楽器の音を奏でる場面があれば・・・なにしろあの平安朝の衣装では華やかなダンスは不可能なのだから、せめて雅で静かな場面くらいはと望んだのは期待のし過ぎだったのか。
舞台展開が早く出演者全て同じような平安貴族の豪華衣装のため、誰がトップスターなのか探すのに困ってしまった。
脚本を手がけた柴田侑宏氏が「平安朝の宮廷や衣装の美しさが宝塚にぴったり。登場人物の多さも魅力だ」と仰っている文を見つけた。
氏の狙いは、「源氏物語絵巻」を宝塚歌劇判として仕上げることのようであった。
「宝塚歌劇版源氏物語絵巻」は、『源氏物語』第一部~第二部の途中までで構成されているが、それは単なる絵巻物に終わらず、禁断の恋による苦悩や平安貴族の愛の形まで簡単なストーリー性を持たせての宝塚らしい構成でもあった。
オーケストラの音はともかく、雅で華麗な『新源氏物語』の次は、思いっきり激しいレビューであった。
宝塚らしい溌剌とした華麗なダンスのショーは、バンドの大音量もなんのその、いつも気分を爽快にさせてくれる。
昨年と同じように歌劇場の一階席前方中央部分の最上と言えるような席を大坂慶應倶楽部の方々で占めていたが、これもひとえに錢高一善会長と小林公一(S.57法:大坂慶應倶楽部評議員:前宝塚歌劇団理事長)氏のお陰である。
いつものことながら大坂慶応倶楽部会員であることに感謝するのみである。
歌劇とレビュー鑑賞後は昨年と同じ3階エスプリホールでのレセプションとなった。
「宝塚歌劇観劇の集い」は、大坂慶応倶楽部の行事としては女性にも参加しやすい行事で今年も
奥様ご同伴で参加されていた会員の方が多くおられた。
平安王朝の豪華絢爛たる時代絵巻から抜け出たような『新源氏物語』の余韻に浸りながら、
心楽しく帰路に着いた。