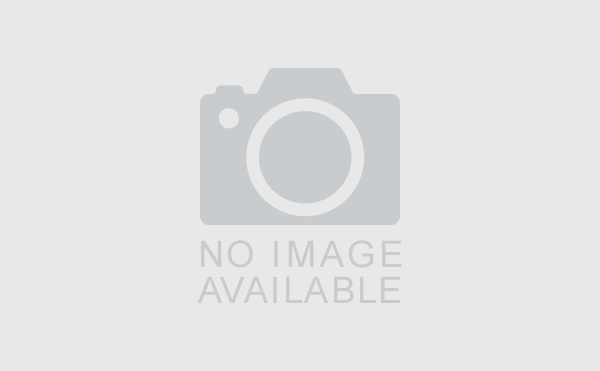白石22 )短編集「季節の装い:夏ーその2」・・・40号
短編集「季節の装い:夏-その2」
白石 常介(81、商卒)
(台湾三田会 顧問)
(3)芒種(ぼうしゅ):穂の出る植物の種をまくころ
<新暦:6月5日~6月20日>
田を耕して水を張り、育てた苗を田に植える季節である。
陽子のふるさとではまさに田植えの季節到来。小さいころは大人が腰をかがめて必死に苗を植えているそばで泥んこになって遊んだものである。
傍らの草木の枝などに付いているピンポン玉くらいの卵から小さなカマキリの子どもがたくさんふ化し始める時期でもある。
田んぼと共存するように小川が寄り添ってさらさらと流れている。陽子は少し大きめの葉っぱを拾ってきてそっと浮かべてみた。あの小川の優しい流れの中にも目には見えない小さな波が複雑にうねっていることを子ども心に目に焼き付けていた。それは大自然の中でごく当たり前に静かにささやきかけているものと思っていた水の流れと真剣に対峙した初めての不思議な記憶でもあった。
そのときどこから来たのかわからないまだ青い梅が1個、上の方からゆっくり目の前をニコッとほほ笑みながら流れていったような感覚を今でも鮮明に覚えている。季節を先取りし、“お先に”ってあいさつしていったような気が・・・。
「ねえ、今度の週末、近くの梅林に行ってみない?」
「おっ、いいねえ、梅林か、って、今はもう梅の花は咲いてないよ」
「そうよ。でもいいの。梅林で昔風情のお花見をね」
「えっ、昔風情の?」
「そう。奈良時代まではお花見っていえば桜ではなくって梅の花を愛でることだったのよ」
「そうなんだ、知らなかった。でもさあ、いくら昔風情っていっても花が咲いてなければさ」
「今は実がなってるでしょ。それを見ながらゆっくりと目を閉じて実がなる前の花を想像してみたりするの。そうすると昔の人がお花見をしている姿が浮かんでくるような気がして」
「おおっ、それっていいね」
「でしょ。それと、今度は目の前に見える現実のお話。梅の実は何に使われるでしょうか」
「当然、梅酒さ、へへ」
「海人らしいわね。青く熟す前の梅は梅酒用、熟してきた梅は梅干し用など、完熟した梅はお砂糖と一緒に煮て梅ジャムに、って、いろいろ用途があるのよ」
「梅雨到来とともに青かった実が黄色くなり赤く熟していく、か。人生の縮図みたいだね」
「でも、寂しいけど、青のまま、黄色のまま、終わってしまうことも・・・。
梅雨の季節に咲く花に栗の花があって、降りしきる雨の中で栗の花が散ることから、梅雨入りを栗花落(ついり・つゆり)とも言うみたいだけど、せっかくの花が途中で散ってしまってはね」
「それも運命なのかな」
梅酒ではないが、酒のつまみに欠かせないのがスルメイカ。日本海を中心に捕れ、細く切ったイカそうめんは絶品である。また、この時期はすすいだように身が白いことからきている夏の白身魚、すずき。新鮮なものは刺身などに。
あっ、だからか、透き通るほどの白い肌の鈴木女史・・・ん?
6月の第3日曜日は父の日である。アメリカで男手ひとつで育てられた女性が父への感謝の気持ちを提唱したのが始まりであり、アメリカでは祝日である。
送る花はバラともユリともいわれているが、日本ではお酒に上記魚介類も喜ばれるかも。花より団子? いやいや、花と団子!
「ねえ、海人は小さいときに何か習っていた?」
「うん。魚の上手な釣り方とか、魚の上手なさばき方とか、魚の上手な食べ方とか」
「そうじゃなくって、お習字とか、ソロバンとか、おけいこ事のこと」
「何だ、あるよ。正月はお餅がうまくってね、思わず習字の書き初めで“うめ~~っ”て書いたら親からお説教、ソロバンをひっくり返してその上に乗って遊んでたらこれまたお説教、怒られた記憶しかないけど」
「それはそうよ、そんなことしたら。でも海人らしいわね。
私はピアノを習ってたの。近くに音楽の先生がいて、6歳のときからときどき教えてもらったわ。昔からお稽古事は6歳の6月6日から始めると上手になるんですって」
「へ~え、でも何で?」
「指を折り曲げて数えるときはね、1、2、3、4、5、そして6はちょうど小指を立てるでしょ。つまり6は子が立つので縁起がいい、っていうことみたい」
「ふ~ん。でも迷信だね、たぶん。で、陽子は何を習ってたの」
「えっ、何を聞いてるのよ、ピアノって言ったでしょ」
「だから、どんな曲を?」
「途中でやめちゃったけど、最後はショパンの英雄・・・」
「おおっ、そこまで行ったのか、大したもんだ、そりゃうまいよ。英雄マヨネーズだろ」
「はあっ?」
(4)夏至(げし):一年で最も昼(日の出から日没まで)が長く、最も夜が短いころ
<新暦:6月21日~7月6日>
対語の冬至(とうじ)とは夜の長さが約5時間も短い夏至。
その短い夜もなんのその、平安京で疫病がはやり無病息災を祈る儀式が行われたのがその起源であるといわれている7月1日より1ヵ月も続く京都の八坂神社の祭礼、祇園祭(ぎおんまつり)。17日の山鉾巡行(やまほこじゅんこう)は最大の見もの。京都の夏の風物詩である。
福岡の博多でも5月の博多どんたくのほかに、毎年7月1日より15日まで博多祇園山笠(はかたぎおんやまかさ)が行われる。特に町ごとに山笠という大きな大きな山車(だし)を繰り出し太鼓をたたきながら櫛田神社(くしだじんじゃ)までの道を走ってその速さを競い合うさまは勇壮そのものである。
「ねえ、去年祇園祭に行ったときに寄った鴨川の川床(かわどこ)料理、あれはよかったわね」
「そうだったね、眺望抜群の夜景レストランって感じだったもん。頭の上を見上げるとまさに天空の星空だったし」
「お天気がよくて最高だったわ。あの時のお料理ではっきり覚えているのは夏の訪れを知らせるアユ料理。柔らかいので骨ごと食べちゃたわよ」
「骨まで愛して、ってか」
「えっ?」
「いや、アユね。あれももちろんよかったけど、僕はやっぱりハモかな。お店の人が言ってたよ、“祇園祭の間、旬が続くから、祭りハモとも呼ばれているんだ”ってね」
「また行きたいわね」
「実は、あの時は金銭的にずいぶん無理したんだ、僕。今度余裕ができたらまたね」
「無理を言ったのは私の方よ。それを何も言わずに受け止めてくれた海人にホレちゃったの・・・あっ、はっ、恥ずかしい」
「ありがと。今度からは無理のない計画を立てようか、二人で相談しながらさ」
「ありがと。そう言ってもらえて」
6月と12月には、罪やけがれを落とす祓(はらえ)の行事があり、6月の行事は夏越の祓(なごしのはらえ)といい、茅(かや)で編んだ直径数メートルの輪をくぐり心身を清め厄を払い無病息災を祈願する“茅(ち)の輪くぐり”が行わわれる。
このころは、紫色の花が花穂にいくつも咲き夏枯草(かごそう)とも呼ばれるウツボグサ、代謝をよくするクエン酸や美肌・かぜ予防・老化抑制のビタミンCがたっぷり入っている夏ミカン、刻んでそうめんの薬味に入れ夏の食欲を引き立てるミョウガなどが旬を迎える。
「ねえねえ、海人、ほかに花は?」
「それはあるよ、たくさんね」
「そうじゃなくって、一番大事なのを忘れてない?」
「この季節の花で?」
「そうよ。“あ”とか“か”がつくの」
「う~ん・・・ありゃりゃりゃりゃ(困ったときの悩みのポーズ)、かかかかかっ(開き直ったときの大笑い)・・・」
「何ひとりで漫才やってるのよ、もうっ」
「ごめん、思い出せなくて。あっ、もしかして菖蒲?」
「そうよ、ったく。それで、何が言いたいか分かった?」
「そうか、やっと分かったよ“いずれあやめかかきつばた”だろ? あっ、だけどね、今度はこっちから質問、いい?」
「どうぞ」
「あのね、菖蒲っていう漢字、これは何て読む?」
「“しょうぶ”でしょ」
「そう。でもね、“あやめ”も同じ漢字なんだ」
「えっ?」
「ごちゃごちゃだから、とりあえずまとめるとこうなんだって」
花の名前 種 類 特 徴 場 所
(漢字)
・あやめ アヤメ科 網目の模様あり 草原などの乾いた土地
(菖蒲)
・しょうぶ サトイモ科 黄緑色の小花密集 湿地
(菖蒲)
・かきつばた アヤメ科 中央に白色あり 池や沼の近くの湿地
(杜若)
「へ~っ、知らなかったわ、ありがとう、って、私が言いたかったのはね」
「うん、分かっているよ“いずれあやめかかきつばた”だろ。(美しさの点で)いずれも素晴らしく優劣を決められない、ってこと」
「そう、それが言いたかったの。いずれ劣らぬ美人がふたりいるでしょ。ひとりっていうかひとつはあやめかかきつばた、もうひとりは、わ、た、し・・・ヘヘ」
「はは~っ、おっしゃる通りでごぜえますだ、花が散るまでは・・・」
「えっ、何かおっしゃいました?」
「いや、何も。ふたり言、いや、独り言でして、はい~っ!」
( 続く)